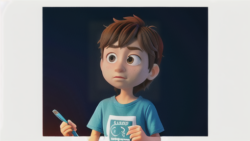深層学習
深層学習 画像を縮小:平均値プーリング
平均値かたまり集めとは、絵の大きさを小さくする技術で、大切な模様を残しながら、処理を軽くする効果があります。これは、絵を細かい正方形のます目に分けて、それぞれのます目の色の濃さの平均を計算することで、新しい小さな絵を作る方法です。たとえば、2×2のます目に絵を分けると、四角の中の四つの点の色を足し合わせて四で割った値が、新しい絵のその部分の色になります。
この処理には、いくつか利点があります。まず、絵の情報量が減るので、後の処理が速くなります。たくさんの計算をしなくて済むので、計算機の負担を軽くできるのです。また、小さな色の違いや画像のざらざらしたノイズの影響を少なくする効果もあります。たとえば、少しだけ色が違う点がいくつかあっても、平均を取れば、その違いが目立たなくなります。これは、絵の模様を認識する作業などで、より正確な結果を得るのに役立ちます。
この方法は、細かいタイルを敷き詰めた絵を遠くから見ることに似ています。近くで見ると一つ一つのタイルの違いがよく分かりますが、遠くから見ると、細かい違いは分からなくなり、全体的な模様だけがはっきりと見えてきます。平均値かたまり集めも同様に、細かい情報を取り除くことで、絵の大切な特徴を際立たせる効果があるのです。このため、物の形を見分けるといった作業に役立ち、人工知能の分野で広く使われています。