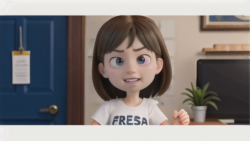機械学習
機械学習 ベイズ統計学入門
私たちの暮らす世界は、予測できない出来事に満ちています。明日の天気予報が外れることもありますし、経済の動向や新しい商品の売れ行きも、確実に言い当てることは難しいものです。このような予測のつかない状況に立ち向かうための強力な道具として、ベイズ統計学があります。ベイズ統計学は、物事がどれくらい確からしいかを確率を使って表し、不確かな事象について推論を行います。
ベイズ統計学の特徴は、過去の経験や知識を確率という形で取り入れることができる点にあります。例えば、過去の天気予報の的中率や、似たような商品の売れ行きといった情報を確率で表し、これらを事前情報として利用します。そして、新しい情報が入ってくるたびに、この事前情報と新しい情報を組み合わせ、より確かな予測へと更新していきます。天気予報で言えば、朝方に雲行きが怪しくなってきたという新たな情報を得れば、雨の確率を高く修正するといった具合です。
従来の統計学では、十分な量のデータが集まらないと、分析が難しいという問題がありました。しかし、ベイズ統計学では、限られたデータでも分析を行うことができます。これは、少ないデータしかない場合でも、過去の経験や専門家の知識といった事前情報を活用できるためです。例えば、新しい薬の効果を調べるための試験では、参加者を多く集めるのが難しい場合があります。ベイズ統計学を使えば、少ない参加者から得られたデータと、過去の類似の薬の効果に関する情報を組み合わせ、新薬の効果や副作用の可能性について確率的な評価を行うことができます。このように、ベイズ統計学は、情報が不足している状況でも、意思決定を助けるための判断材料を提供してくれるのです。