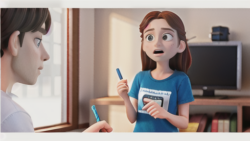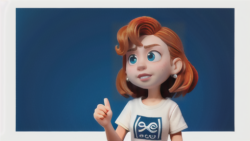機械学習
機械学習 複数の感覚を統合するAI
人が外界を知るには、様々な感覚を使います。例えば、目で見て物の形や色を認識し、耳で聞いて音の高低やリズムを感じ取ったり、皮膚で触れて物の硬さや温度を確かめたりします。このように、五感をはじめとする感覚を通して得られる情報は、それぞれ異なる性質を持っています。この情報の種類のことを、人工知能の分野では「様式」という意味の「モダリティ」という言葉で表します。
人工知能も人間と同じように、様々なモダリティの情報を取り扱います。写真や絵のような図形情報もあれば、話し声や音楽のような音声情報もあります。文字で書かれた文章や記号のような言語情報も、人工知能にとっては重要な情報源です。さらに、温度や圧力、動きなどを計測した数値情報も、人工知能が利用するモダリティの一つです。
それぞれのモダリティには、適した処理方法があります。例えば、図形情報を扱う場合には、画像認識技術を用いて、写真に写っている物体が何かを判別したり、図形の特徴を抽出したりします。音声情報を扱う場合は、音声認識技術を用いて、音声データを文字に変換したり、話者の感情を分析したりします。言語情報を扱う場合は、自然言語処理技術を用いて、文章の意味を理解したり、文章を要約したりします。数値情報を扱う場合は、統計的手法や機械学習を用いて、データの傾向を分析したり、未来の値を予測したりします。
このように、人工知能は様々なモダリティの情報を組み合わせて、より高度な処理を行うことができます。例えば、自動運転車の場合、カメラで捉えた図形情報、レーダーで計測した数値情報、GPSで得られた位置情報などを組み合わせて、周囲の状況を認識し、安全に走行するための判断を行います。また、医療診断支援システムの場合、患者の画像情報、検査データの数値情報、電子カルテの言語情報を組み合わせて、病気の診断を支援します。このように、複数のモダリティを組み合わせることで、人工知能はより複雑な問題を解決することが可能になります。