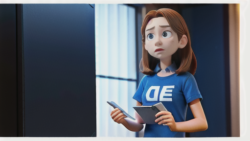 深層学習
深層学習 画像処理におけるパディングの役割
写真の縁に額縁を付けるように、画像の周囲に余白を追加する処理をパディングと言います。この余白部分には、あらかじめ決められた値を持つ画素が配置されます。まるで額縁のように、元の画像を囲むことで、画像全体の大きさを調整します。この余白部分の画素は、元の画像には含まれていない、処理をスムーズに進めるための追加部分です。
パディングを使う場面の一つに、畳み込みニューラルネットワーク(CNN)の処理が挙げられます。CNNは、画像の中から重要な特徴を見つけるために、畳み込みと呼ばれる計算を何度も繰り返します。この畳み込み計算を繰り返すたびに、処理対象の画像サイズは小さくなってしまいます。このため、何度も畳み込み計算を行うと、最終的には画像が小さくなりすぎて、重要な情報が失われてしまう可能性があります。そこで、パディングを用いて画像の周りに余白を追加することで、画像サイズの縮小を防ぎ、より多くの畳み込み計算を可能にします。
パディングには、画像の端の情報を適切に捉える効果もあります。畳み込み計算では、小さな窓を画像の上でスライドさせながら計算を行います。パディングがない場合、画像の端にある画素は、窓の中心に来る回数が少なくなり、十分に情報が利用されません。しかし、パディングで余白を追加することで、画像の端の画素も窓の中心に来る回数が増え、画像全体の情報を満遍なく使えるようになります。このように、パディングは、画像処理において、畳み込み計算を円滑に進め、画像の端の情報も有効に活用するための重要な技術です。























