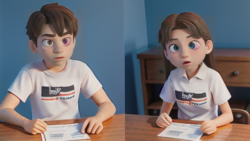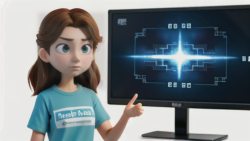 アルゴリズム
アルゴリズム 移動平均でデータを見やすくする
移動平均は、データのばらつきを和らげ、全体的な流れを掴むための統計的手法です。一定の期間に含まれる数値の平均を次々と計算し、それを繋げていくことで、滑らかな曲線を描きます。この曲線を見ることで、細かい変動に惑わされずに、データの大きな動きや方向性を知ることができます。
例えば、毎日の気温の変化を想像してみてください。日によって気温は上下しますが、一ヶ月間の移動平均を見ることで、季節による気温の変化という大きな流れを把握できます。日々の細かい気温の変化は移動平均の中では和らげられ、滑らかな曲線として表現されます。
この手法は、株価の分析など、様々な分野で使われています。株価は日々大きく変動しますが、移動平均を使うことで短期的な変動の影響を抑え、長期的な傾向を捉えることが可能です。例えば、5日間の移動平均であれば、毎日、過去5日間の株価の平均を計算し、それをグラフにプロットします。
移動平均を計算する期間の長さを変えることで、分析の目的に合わせた使い方ができます。短い期間の移動平均は、直近のデータの変化に敏感に反応し、細かい動きを捉えることができます。一方、長い期間の移動平均は、細かい変化の影響を受けにくく、長期的な傾向を把握するのに役立ちます。
移動平均は、データの分析や予測を簡単にする便利な道具ですが、万能ではありません。過去のデータに基づいて計算されるため、未来の予測が必ずしも正しいとは限りません。また、移動平均を使う際の期間の設定は分析の目的に合わせて適切に選ぶ必要があります。適切な期間設定を行うことで、より効果的にデータの傾向を把握し、将来の予測に役立てることができるでしょう。